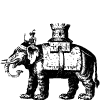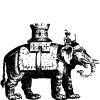Tweet
第6回 ガリガリ君の夏
ようやく暑さも一段落したようだ。今年の夏は、とにかく暑かった。
暑い夏の日、「ガリガリ君」(赤城乳業の人気の氷菓のことだ)を見ると、ある一場面を思い出す。と言っても、コンビニのアイスケースに入りたがる若者たちのことではない。患者のことは何ひとつわかっていないかもしれない、ということを心に留めたある一場面だ。
患者の立場に立つことができるか?
「患者の立場に立って考えなさい」とは、古くからの医学の教えである。特に、患者に対する言動や態度が医者として相応しくないとみなされた場合、今でもこのような言葉が飛び交うことがある。
われわれが診察室でよく用いる技法「患者中心の医療の方法」1では、診断に必要な「疾患」の情報だけではなく、診察の導入部分から「病いの体験」の情報にも配慮すべきであることを教えている。すなわち、いかに悩み苦しみ、どんな病気を怖れ、日常生活にどんな影響があり、そしてどのような医療を望むか、という点について、よく話してもらうことが重要であるというのだ。
患者の立場に立つこと。患者を中心に考えること。―そのことが現代医療の基本的な教えとなっている。しかし、それは本当なのだろうか。この教えを無下に否定するつもりは毛頭ないが、ここで立ち止まって少し考えてみたい。
伝聞の集積という体験
「患者の立場に立って考えなさい」という教えの裏には、暗に患者になるということはどういうことかを医者なら適切にイメージできるはず、ということが前提となっている。
「患者中心の医療の方法」に至っては、「病いの体験」について患者に詳しく話してもらうだけで医者なら適切に理解できるはず、ということが前提になっている。少なくとも、これには患者が自らの苦しみの体験を自らコトバで表現することができる、ということがそれ以前の前提となるだろう。
はたして、このような前提を置くことは現実的なのだろうか?
医者は多くの場合、診断や治療する病気を自ら体験していない。大抵は、患者やその家族らの伝聞の集積が体験として積み上がっているだけだ。
もちろん、伝聞の体験がまったくない人に比べれば、医者のほうがイメージすることが容易なのかもしれない。しかし、それはあくまでも「症例の経験」という伝聞情報の集積に過ぎないのだ。
うまく伝えられる患者もいれば、そうではない患者もいる。病気によっては自らの体験を他人に伝えられなくなることもある。臨終の体験については、原理的に直接伝聞することはできない。「死人に口なし」ということわざもあるが、残念ながら医療は、臨終まで体験したユーザーの声を生かすことができないのである。伝聞情報から得られることは、そもそもごく限られているのだ。
しかし、伝聞の集積という体験があるだけで、ひとくくりに医者は患者のことがわかるはずという暗黙の前提があるとしたら、そこに一抹の不安を感じる。
わずらった当事者でなければわからないことは、たくさんあるはずだからだ。
暑い夏の一場面
あれから何年が過ぎただろうか。ある暑い夏の日、末期がんと診断された初老の女性の話である。町の病院では、もはやがんに対する治療のほどこしようがなく、余命1か月と宣告されて自宅に帰ってきた。どの部位の末期がんだったかさえ、記憶も定かではないが、病状の割に鎮痛剤をほとんど使用していなかったことだけは印象に残っている。女性は身寄りのない一人暮らしで、収入もなく生活保護を受けていた。まもなく、私は訪問診療を担当することとなった。
自宅の窓からは、隣接する保育園の園児の楽しそうな声がこだましている。「子どもたちの声が聞こえると、何となく落ち着いた気分になれます。」と、保育士として長年働いてきた彼女らしい。
暮らしぶりはとても慎ましやかで、夜もほとんど電灯を使用せず、冷房はもちろん冷蔵庫も持っていなかった。暑い夏、熱中症を心配する訪問介護員の言葉にも、「お国のお金をもらっているのだから、大切に使わないと。」と口癖のように話しながら、静かに笑った。(生活保護受給者の多くは、このような気高い方々ではないかと想像する。)
介護支援専門員も訪問看護師もみな、そのような人となりを理解して対応していた。
訪問介護員は体調を心配し、ポットに氷を入れて持参していた。「冷たいものがお好きなそうなので、毎日持ってきています。」その対応に、彼女はたいへん喜んでいた様子だった。しかし、どんなに食べられなくなっても、痛みが強くなっても、気丈に振る舞い、ほとんど自分から何かが欲しいと訴えることはなかった。
ある日、私が自宅に訪問に伺うと、彼女がためらいがちに、そして上品に話しはじめた。
「先生、どうしてもひとつだけお願いしたいことがあるんです。入院していた頃からずっと我慢していて、どうしても言えなかったことです。」
「どんなことでもいいですよ。話してください。」
「みなさん、とても親切にしてくれてありがたかったのですが、言おう言おうと思って、言えなくて我慢してたことなのですが。先生にこんなこと言っていいのかどうか、わかりませんが・・・ガリガリ君ってアイスがありますよね。あれがどうしても食べたいんです。私は昔からガリガリ君が大好きで。そこのコンビニにも売っていますよね。」
「どんなことでもいいですよ。話してください。」
「みなさん、とても親切にしてくれてありがたかったのですが、言おう言おうと思って、言えなくて我慢してたことなのですが。先生にこんなこと言っていいのかどうか、わかりませんが・・・ガリガリ君ってアイスがありますよね。あれがどうしても食べたいんです。私は昔からガリガリ君が大好きで。そこのコンビニにも売っていますよね。」
「冷たいものが食べたい」という彼女の希望が、実はガリガリ君が食べたいという希望だったことが判明する。まもなくガリガリ君を口にすることができた彼女は(と言っても、残念ながらその場に居合わせることができなかったのだが)、その数日後に息をひきとった。
彼女の願いはガリガリ君?
亡くなる前にガリガリ君の希望を聞き出すことができてよかった。そして希望を叶えてあげられてよかった。単にそういう美談で済ませてよいのだろうか。未だにすっきりしない何かが残る。
彼女の願いは本当にガリガリ君だったのだろうか?
なんとか思い出そうとする。彼女がどんな表情で、その言葉を発していたのか。そして、なんとか想像する。彼女がガリガリ君を一口だけ口にした時、どんな表情だったのか。
わかったつもりになってはいけない。医者は患者の対岸にいる。患者のことは、何ひとつわかっていないかもしれないのだ。
次々と過ぎ去っていく体験を積み重ねる、何か別の方法があるのかもしれない。
文献
1. Stewart M, Brown JB, Weston WW, McWhinney I, McWilliam CL, Freeman TR. Patient-centered medicine: transforming the clinical method. London: Sage Publications, 1995