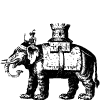Tweet
第15回 終末期は摩擦ばかり
私たちが受け持つ在宅医療の現場では、進行がんなどの終末期医療に関わることが多い。病院での急性期の治療が一段落し、患者が自宅で過ごせるようになることは、一見幸せなことのように思える。
そう、家族に見守られるなどの一定の条件が満たされているわけであるから、ある意味ありがたい境遇にあるともいえるのだ。
しかし、病院での治療に一縷の望みを持っている人にとってはどうであろうか。退院することはむしろ見放されたように感じ、不安と葛藤の日々になるかもしれない。
自宅に帰ってきても、しきりにまた病院に戻りたいと訴える人もいる。自宅に帰れることが幸せ、と手放しで喜べるとは限らないのである。
在宅医療と病院医療の狭間で、終末期にも摩擦は絶えない。
終末期というコトバ
そもそも、終末期というのは、何か不思議なコトバだ。
人の死は予測できるものではない。亡くなってから、振り返ってはじめて、終末期がどのあたりからだったのだ、とわかる性質のものだろう。
しかし、進行がんなど、余命がある程度予測がつくものについては、予測から終末期であると判断される。これはもちろん便宜的に決められるものであるが、どこまでが終末期ではなくて、どこからが終末期であるという、はっきりとした線引きがあるわけではない。
さらに、予後の見積もりというのは、とても難しいものである。あと余命半年程度と言われても、実際には1カ月以内のこともあれば、1年以上元気で過ごされることもある。いくら医療が進歩したとはいえ、いまだ「お迎えがくる時期」を正確に予測することはできないのだ。
先のことが予測できないから、どうしていいかわからない。本人も家族も、そして医療者も、頭を悩ませながら、日々過ごしている。
逃げるように始まる在宅医療
「もう病院へは絶対戻りたくない。」
その様子はまるで、病院から逃げ帰ってきたかのようだ。
私も病院に勤務し、このような患者を送り出す側にいたことがある。当時から、退院後に恨み言のひとつでも言う患者はいるだろうとは、うすうす感じていた。しかし、受け入れる側になってはじめて、そのような患者が、想像したよりはるかに多いことを知った。
病院での治療はつらいものだ。病院では治療が優先されるため、緩和ケアにまで手が回っていないことも多い。さらに、病状は日々進行していく。逃げ帰りたくなる気持ちもわからなくもない。苦しいのだ。
退院してきた終末期の患者に対して、私たちが訪問診療で最初にやる仕事は、痛みや苦痛、そして不安の緩和である。
在宅医療での関わりは短い。退院してから、訪問診療で初対面ということがほとんどだが、終末期ともなれば、お会いしてから数カ月、数日、時には数時間ということもある。
短い時間でいかに信頼関係を構築していくか、課題でもあり、日々模索を続けている。
「死ぬからこそある医療」1へ
退院して間もないある終末期の男性患者を思い出す。訪問診療で伺ったところ、病状が進行して食欲がなく、ほとんど何も口にできない状態となった。患者を案じながらも、介護している妻が尋ねた。
「先生、ビール飲ませてもいいでしょうか?この人、入院している時からビールが飲みたい、飲みたいって。病院ではだめだって言われたから。」
これまでの入院生活では、食事内容を厳しく制限されていたようである。しかし、もはやこのような状態では、ビールの制限は予後に何の影響も与えないだろう。もちろんどうぞ、と許可した。
そして、男性患者はその数日後に亡くなられた。臨終の場で、妻が涙ながらに語った。
「本当においしそうにビールを飲んでいました。数口だけでしたが、飲ませてあげられてよかったです。」
ビールの味は格別だったかどうか、わからない。しかし、飲ませてあげることができて、家族も私も、ほんの少しだけ救われた気がした。
一分一秒でも死なないようにする医療に、どれだけの価値があるのだろうか。そして、死ぬからこそ、医療にはまだできることが他にもあるのかもしれない。
終末期は摩擦ばかりだ。
文献
1. 名郷直樹. 「健康第一」は間違っている. 筑摩書房, 東京, 2014