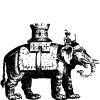Tweet
第1回 象について何がしか書く
村上春樹の処女作『風の歌を聴け』は以下のような一節から始まる。
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望というようなものが存在しないようにね。」
僕が大学生のころ偶然に知り合ったある作家は僕に向かってそう言った。僕がその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれはある種の慰めとしてとることも可能であった。完璧な文章なんて存在しない、と。
しかし、それでもやはり何かを書くという段になると、いつも絶望的な気分に襲われることになった。僕に書くことのできる領域はあまりにも限られたものだったからだ。たとえば象について何かが書けたとしても、象使いについては何も書けないかもしれない。そういうことだ。
僕が大学生のころ偶然に知り合ったある作家は僕に向かってそう言った。僕がその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれはある種の慰めとしてとることも可能であった。完璧な文章なんて存在しない、と。
しかし、それでもやはり何かを書くという段になると、いつも絶望的な気分に襲われることになった。僕に書くことのできる領域はあまりにも限られたものだったからだ。たとえば象について何かが書けたとしても、象使いについては何も書けないかもしれない。そういうことだ。
私は村上春樹の熱心な読者ではない。しかし、この一節だけは、くり返しくり返し、私の脳裏をかすめ、私自身を何か不安にさせる。
『「完璧な診断などといったものは存在しない。完璧な絶望というようなものが存在しないようにね。」
僕が大学生のころ偶然に知り合ったある医者は僕に向かってそう言った。僕がその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれはある種の慰めとしてとることも可能であった。完璧な診断なんて存在しない、と。
しかし、それでもやはり何かを診断するという段になると、いつも絶望的な気分に襲われることになった。僕に診断できる領域はあまりにも限られたものだったからだ。たとえば象について何かが診断できたとしても、象使いについては何も診断できないかもしれない。そういうことだ。』
僕が大学生のころ偶然に知り合ったある医者は僕に向かってそう言った。僕がその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれはある種の慰めとしてとることも可能であった。完璧な診断なんて存在しない、と。
しかし、それでもやはり何かを診断するという段になると、いつも絶望的な気分に襲われることになった。僕に診断できる領域はあまりにも限られたものだったからだ。たとえば象について何かが診断できたとしても、象使いについては何も診断できないかもしれない。そういうことだ。』
「インフルエンザを心配する患者を前にして、実のところあなたは、インフルエンザかもしれないが、そうではないかもしれない、としか言えない、とかなんとか言った医者。あなたは村上春樹?」、Twitterでそんなつぶやきを読み(元の発言がどうしても探し出せない)、医者の診断という作業と、冒頭の一節が重なる。村上春樹は、私のことを書いたのではないだろうか。まあ、そんなわけはないのであるが。
そして、さらに問題はややこしい。仮に完璧な文章があるとして、誰がそれを完璧な文章だと読むのか。目の前の患者が完璧なインフルエンザだったとしても、その完璧なインフルエンザということが、患者にどう伝わるかなんてことは全く分かったことじゃない。
それでもまだインフルエンザなんてのはわかりやすい。鼻の奥の粘液を採ってきて、検査にかけて、陽性と出ればインフルエンザ、そんなわかりやすい診断方法があるからだ。実際、陽性の検査結果を示して、「今、私はあなたを完璧にインフルエンザと診断しました」といっても、患者の多くはそれなりに納得するかもしれない。
しかし、このわかりやすいインフルエンザの診断であっても、完璧な診断は、ある種の絶望である。たとえばその患者の症状を確かめると、特に何の症状もなかった。インフルエンザの人と一緒にいたのでただ心配なだけだったということがありうるからだ。
もう一つ考えてみよう。高血圧。完璧な高血圧の診断。これはもう最初から絶望だ。140mmHg以上を高血圧とする、なんていうのだが、それでは139mmHgは高血圧ではないのか。もう最初から絶望的である。
それでも、今、僕は書こうと思う。完璧な医療なんて存在しないのだから。それを慰めとして、診断について、治療について、予防について書こうと思う。
「もちろん問題は何一つ解決していないし、書き終えた時点でもあるいは事態は全く同じということになるかもしれない。結局のところ、文章を書くことは自己療養の手段ではなく、自己療養へのささやかな試みにしか過ぎないからだ。」
「うまくいけばずっと先に、何年か何十年か先に、救済された自分を発見するかもしれない、と。そしてその時、象は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう。」
「うまくいけばずっと先に、何年か何十年か先に、救済された自分を発見するかもしれない、と。そしてその時、象は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう。」
村上春樹が言うように、象使いについては何も書けないかもしれないが、象について何がしか書けるかもしれない、ならば少し書いてみよう、というのが本連載の目的だ。
『「僕は医療についての多くをサケタ・キヨトに学んだ。ほとんど全部というべきかもしれない。不幸なことにサケタ・キヨト自身はすべての意味で不毛な作家であった。診察してもらえばわかる。説明はわかり辛く、理屈は出鱈目で、喩は稚拙だった」』
『サケタ・キヨトがよい医療についてこんなふうに書いている。「診断するという作業は、とりもなおさず自分と自分をとりまく事物との距離を確認することである。必要なものは感性ではなく、ものさしだ」』
『サケタ・キヨトがよい医療についてこんなふうに書いている。「診断するという作業は、とりもなおさず自分と自分をとりまく事物との距離を確認することである。必要なものは感性ではなく、ものさしだ」』
ほとんど小説のパクリではじめたが、どこまで行ってもパクリに過ぎないかもしれない。それでも、今、僕は書こうと思う。